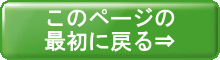�R���e���c�ꗗ�͂�����ɂȂ�܂��B
���Q�l�ɂ���ĉ�������
�z�[���y�[�W�������̊F�l�A�͂��߂܂��āB
�R�����⍑�s�ŏ��K�̓f�C�T�[�r�X���^�c���Ă��铡�{�ł��B
7�N�Ԃ̌���̌o�����o��15�N�O�ɓƗ����Ĉȗ��A��ɐl��s���ɔY�܂���Ă��܂����B
�l��s���ƌ����Ă���K�͎{�݂ɂ͑�K�͎{�݂Ȃ�́A���K�͎{�݂ɂ͏��K�͎{�݂Ȃ�̔Y�݂�����Ǝv���܂��B
���������X�^�b�t������Ȃ����Ƃ�����x�ɐF�X�ƍH�v�����Ă��܂����B�����ł��ǂ�Ȏ{�݂ł��ʗp����Ǝv���H�v�������Ă݂����Ǝv���܂��B
�����������玄�����̌o���������ł��F����̂����ɗ��Ă邩������܂���B���Q�l�ɂ��Ē�����K���ł��B
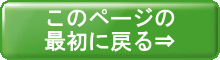
�l��s���ƂЂƂ����Ɍ����Ă��A�������̎{�݂̏�����K�v������܂��B
����Ȃ��̂́A�P�A�̌���̃��[�_�[��Ǘ��҂��ł���l�i�l�ށj�Ȃ̂��A�őO���ŃP�A�ɂ�������E(�l���j�ł����H
���̃R���e���c�ł̓P�A�̌���̃��[�_�[��Ǘ��҂��ł���l�i�l�ށj������Ƃ����O��ŁA�őO���ŃP�A�ɂ�������E�̐l��������Ȃ��Ƃ��̍H�v�ɂ��ď����Ă����܂��B
�Ȃ��Ȃ�A���[�_�[��Ǘ��҂��ł���l(�l�ށj�����Ȃ��̂́A�H�v�����ł͂����ɂ͉��Ƃ��Ȃ�Ȃ�����ł�(�j
���̃R���e���c�Łw���[�_�[��Ǘ��҂��ł���l(�l�ށj�̈�ĕ��x�Ȃ�ďo��������̂ł����A�܂����������Ď��M������܂���B
����Ȑl�ނ���Ă����Ƃ���������ł�(�j
���[�_�[��Ǘ��҂��ł���l(�l�ށj���琬������@��m�肽�����͐��̍u���������������Ǝv���܂��B
������Ƙb�͂���܂������A�Ȃ����[�_�[��Ǘ��҂��ł���l���K�v����������܂��B
�w
���S�Ȃ��g�D�͋@�\���Ȃ��x
�h�c�싅����g���ăv���싅�E�ɑ���Ȃ���т��c���A��N�S���Ȃ�ꂽ
�v���싅�̖����u�쑺����x����̌��t�ł��B
�u
�G�[�X��4�ԂƂ��������{�ɂȂ�I�肪���Ȃ��Ƒg�D�͋@�\���Ȃ��v�Ƃ����Ӗ����Ǝv���܂��B
�G�[�X��4�Ԃ���쌻��ɋ��߂�̂͂������ɖ���������Ǝv���̂ŁA
���́A��쌻��ɓ��Ă͂߂Ă������߂��܂����B
�u
���f�����邱�Ƃ��ł��āA�ӔC�ƂƂ�o��̂���l�����Ȃ��g�D�͋@�\���Ȃ��v
�����l���郊�[�_�[��Ǘ��҂��ł���l�Ƃ����̂́A�o��������Ƃ��N���Ƃ���E������Ƃ��ł͂Ȃ�
�u
���f�����邱�Ƃ��ł��āA�ӔC�ƂƂ�o��̂���l�v
�ɂȂ�܂��B
�u����Ȑl���Ȃ��c�v�����v���Ă��܂��H
���₢��A�e�{�݂Ɉ�l���炢�͂���͂��ł���A���f�ł���l�́B
����̂́A�u�ӔC�����v�ƌ�����l�ł��B�N�ł����ł���ːӔC�����̂́B
�ǂ����܂��傤�c���ɂ��Ȃ��������ł��B�O���[�]�[���ł����܂��傤(�j
�Ȃ����Ƃ����ƁA
�����̎����Ă��鎑�i���E�ȏ�̐ӔC�͖���Ȃ������ł��B
�u�ӔC�����v����Ō��f���āA��i��Ǘ��҂�o�c�҂ɐӔC���ۓ������܂��傤(�j
�܁A�����͏�k�Ŕ����͖{�C�ł��B
�����l���Ȃ��ƑO�ɐi�߂܂���ˁB
�Ƃ������ƂŁA����������
���f�ł���l������O��ŁA
�l��s��������H�v�ɂ��ď����Ă����܂��ˁB
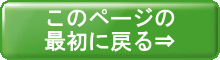
�F����̌���ōs���Ă���Ɩ��ɂ͂ǂ�Ȃ��̂�����܂����H
�Ɩ����Ă����Ɣ��R�Ƃ��Ă��܂����ˁc
��̓I�Ɍ����ƁA���ڗ��p�҂ɊW���邱�Ƃ��܂߂āA����̃X�P�W���[���ɑg�ݍ��܂ꂽ���Ȃ��̎d���̂��Ƃł��B

�@

�l��s��������ɂ́A����̃X�P�W���[���ɑg�ݍ��܂ꂽ���Ȃ��̎d����
�@���E�����ׂ��d��
�A���E�łȂ��Ă�(�{�����e�B�A�����O���Ȃǁj�o����d��
�B����ł���Ă��邯�ǎ��͂��Ȃ��Ă�����Ȃ��d��
|
�ɕ����čl���܂��傤�B
�@�ɂ��Ă͂킩��܂���ˁB�H����r��������̃P�A�A�F�m�ǂ̕��������Ă���Ƃ��̑Ή����ł��B
�A�ɂ��ẮA�e�{�݂ňႢ������Ƃ͎v���̂ł����A�H���̏�����V�[�c�����A����A�{�����e�B�A����ł��Ή��ł��闘�p�҂̎�����̎x���Ȃǂ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���͇B�ł�(�j
����ł���Ă��邯�ǎ��͂��Ȃ��Ă�����Ȃ��d��
����܂�͂����茾���ƌ�����̂Ō��������Ȃ��̂ł����A
�Ⴆ��
10����15���ɂȂ�ƁA���������c����邱�Ƃ̑���������S���ɏo�� 1�x�N�����Ē��ւ������Ă܂��Q�����鑁���̗���� �����̌��� �ُ�ɑ����C�x���g�Ƃ��̏��� �C�x���g�ł̐E���̏o����
|
���R�͈ȉ��̂悤�ɂȂ�܂��B
�����⋋�Ȃ牽��ނ��p�ӂ��āA���݂����Ȃ���̈��݂����Ȃ鎞�ɂ����������Ӗ�������B �N�����Ԃ��ꏏ�ɂ��邩�炱���Ȃ�B�o���o���ɋN���Ă�������B �a�@�ɓ��@���Ă�l�ł���������Ȃ��B�������ė[�������Ƃ��B����K�v�̂��鎞�ɑ�����������I�B �{�ݒ��̑ΊO�I�ȃA�s�[���ׂ̈ɂ���Ă��邱�Ƃ�����(�j
���E�ɂ���Ȏ��Ԃ͂Ȃ��I
��̂����r���[�ȏo�����ɂȂ邩��(�j
|
���������Ɩ��������������ŁA�����͐l��s���������ł���͂��ł��B
�Q�l�ɂ���ĉ������ˁI
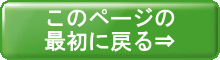
�i���Ƃ����O�̏����̂��Ƃł��B
���炩���ߐl�肪����Ȃ��Ȃ鎞�Ԃ�\�����āA�����Ȃ�Ȃ��悤�Ɏ��ł��Ă����Ƃ������������܂��B
�Ⴆ�A
�@���N�̏����i�������邩���܂߂āj������Ă����B
�A���̐l�͂��̎��ԂɃg�C���ɍs�����낤����A��ɓ��邽�߂ɁA���̑O�ɕʂ̎d�����ς܂��Ă������B
�B���̐l�͂����Ƃ��̎��ԂɎ{�݂��яo�����낤(�j����A�ԂƉ^�]��̎�z�����Ă������B
|
�l�Ƃ��Ă��i���͑厖�ł����A�{�݂Ƃ��Ă��`�[���ł̒i��������Ă����ƁA
���̏u�Ԃ̐l��s���̉����ɂȂ���܂��B
�Q�l�ɂ���ĉ�������!
�F����̎{�݂ł�����܂��H
�l������Ă�͂��̎��ԂɁA�Ȃ����l������Ȃ�(�j
���������A���̗ǂ��E�����ł܂��Ă��邱�Ƃ������ł��B�d������`���Ă���ӂ�����āB
���E�̎d���ŁA��l�łȂ��Ƃł��Ȃ��d���͂قƂ�ǂ���܂����B���x�̏d���l�̉�͓�l�K�v��������܂��A�������Ƃ��Ă���l�K�v�Ȃ̂͏����̎��Ԃ������肵�܂��B
����ȊO�̎��ԂɌł܂��Ďd�������Ă���l�͂�Ƃ肪�����ł��B���͉ɂȂ�ł��B�d����҂��Ă��܂�(�j
���f�ł��郊�[�_�[���A�d��������U���Ă����܂��傤�I
���ꂾ���Ől����l�����܂��B
���ЎQ�l�ɂ���ĉ������I
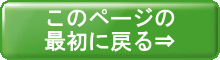
�P�A�̎��Ԃ����炷�c���������ǂ��������Ƃł��傤�H
�Ⴆ�g�C���U�����ɍl���Ă݂܂��傤�B
���N�̑O�Ƀg�C���̐��|��������P�[�X������Ǝv���܂��B
�u�݂Ȃ���A���������Ń��N���n�܂�܂�����g�C���ɍs���Ă����Ă��������I�v
���̂悤���傫�Ȑ��œ`����Ƃǂ��Ȃ�܂����H
�E3�����Ȃ��g�C����10�l����ĂɌ������B
�E�E������l�������Ȃ��̂ɁA����K�v�Ȃ��N���O�l���g�C���Ɍ������Ă��܂��B
|
�����I�ɕs�\�Ȃ��Ƃ��N���Ă��܂��̂ł��B
�l��s���̔����ł��B
�����Ȃ�Ȃ����߂ɂ́A
�X�̂��N���̃g�C���̊Ԋu���ɓ���K�v���A�����ăg�C���̎��Ԃ̒���(�j���l�����Ȃ���g�C���ɗU�����鎞�Ԃ����炷�K�v�������̂ł��B
���������Ή��́A����ł��N���̓�����m���Ă���F����Ȃ���Ȃ��ł���͂��ł��B
�����đ�Ȃ��Ƃ́A
��l��l�ɏ����Ȑ��ł�����(�j�����|�������Ƃł��B
�l�́A�N�����g�C���ɍs���Ǝ������s�������Ȃ�܂�����A��ɏ����Ȑ��Ő����|���܂��傤�ˁI
�܂�����ȃP�[�X�͂ǂ��ł��傤���B
�X�^�b�t��4�l�A�H������K�v�Ȑl��5�l����Ƃ��܂��B
�ǂ����܂��傤�c
�u��l�œ�l��������������I�v
�u���`�A�������ł��ˁc���ă_���ł���A���������̂�
���̂̂����ł��I�v
�u���Ⴀ�ǂ���������́H�v
����ƈꏏ�ł��B
�H���̎��Ԃ����炵�܂��傤�B
�N����l�͐H���������Ȃ��Ă��x���Ȃ��Ă����������̂Ȃ��l������͂��ł��B
��l�ŐH�ׂĂ����C�Ȑl�A��l���Ɠ{�肾���l�A���H�������l�ȂǁA���N���̓������l�����Ȃ���l���Ă݂ĉ������ˁI
�u�r���̎��Ԃ����炷�v�u�H�����Ԃ����炷�v�܂ł��܂����̂ŁA�����̎��Ԃ����炵�Ă݂܂��傤��(�j
�Ⴆ�A�f�C�T�[�r�X�̃T�[�r�X���Ԃ�7���Ԃ������Ƃ��܂��B
���H��1���Ԃ�����Ƃ��Ă���ȊO�̎��Ԃ�6���ԂɂȂ�܂��ˁB
���̓��ɓ������闘�p�҂�10�l����Ƃ���ƁA6����(360���j��10�l��36��
���̏ꍇ�A�P�l����̓����Ɋ|�����鎞�Ԃ�36���ɂȂ�܂��B
������A�ʏ�͒��H�ɏ[�Ă���1���Ԃ̊Ԃɂ��������s���Ă���Ƃ�����ǂ��Ȃ�ł��傤�H
7����(420��)��10�l��42���@�ł���ˁB
1�l����̓����Ɋ|�����鎞�Ԃ�42���ɂȂ�܂���ˁB
1�l����̎��Ԃ�6�������܂����B���̎��ԂłȂɂ��ʂ̃P�A���o���邩������܂������B
�u���Ⴀ���H���Ԃɂ����C�ɓ���l�̐H���͂ǂ�����́H�v
���Ԃ����炵�ĐH�ׂĒ����̂ł��B
�u�݂�Ȃƈꏏ�ɐH�ׂ��Ȃ��͉̂���������Ȃ��ł����H�v
���̓����͂����ł��B
���ԓ��ɏI��点�悤�ƁA���D�ɂ�����������u���邩��オ��܂��傤(�j�v�̕�������������Ȃ��ł����H
���̐l�̖{���̃j�[�Y�́A
�u���߂�ꂽ���Ԃɂ����C�ɓ��肽���v�ł͂Ȃ��A
�u������肨���C�ɓ��肽���v�̂͂��ł��B
�u���߂�ꂽ���ԂɐH�����������v�ł͂Ȃ��A
�u�������ꂸ�ɂ������H�����������v�̂͂��ł��B
|
���̂悤�ɁA
�������ԂɃP�A�������A���p�҂̓������l�����Ȃ���P�A�̎��Ԃ����炷���ƂŁA���Ȃ��l���ʼn\�ɂȂ����Ƃ�����܂��B
�܂��A�P�A�ɂ������鎞�Ԃ������܂��̂ŁA���ЎQ�l�ɂ���ĉ������ˁI
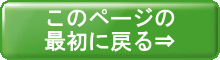
�D�揇�ʂ��Ăǂ��������Ƃł��傤���H
���N���ւ̒��ڂ̃P�A������ȊO�̋Ɩ��ɗD�悷��͓̂��R�̂��Ƃł��̂ŁA�X�ł͊������܂��B
�����Ō��������̂́A�������邨�N���ւ̃P�A�̒��ł��D�揇�ʂ����ĉ����Ă����Ƃ������Ƃł��B
�H����r���E�����̃P�A�ł����A�ŗD�悳���̂͂������r���P�A�ɂȂ�܂��B
�u�H�����ł����Ă��A�A�ӕֈӂ�i�����璆�f���ăg�C���ɘA��Ă����v
������w�r��(�r�ցj�ŗD��̌����x�Ƃ����܂��̂ł����͊ԈႦ�Ȃ��ł��������ˁI
�ꌩ������Ȃ悤�ł����A�r�A��r�ւ̎��s�̌�n��������Ƃ��Ɏ���鎞�Ԃ�l��ɔ�ׂ���債�����Ƃ͂���܂����B
�ł́A���N���ɂ��肢����邱�Ƃ�ʂ̎�����ɂ��Ă͂ǂ�������悢�̂ł��傤���H
����́A��T�ɂ͌����܂���B
�Q�l�܂łɎ��̍l�����������܂��ƁA��{�I�ɂ͗��܂ꂽ���Ԃ�D�����܂��B
���ꂾ�ƁA�F�X�ȕs�s���������Ă��܂����ɂ́A���O�ɂ��N���ƌ����ď��Ԃ�ς��Ă��炤���Ƃ�����܂��B
���̎��ɏd�v�Ȃ̂́A�g���u���ɂȂ�Ȃ��悤�ɍאS�̒��ӂ����Ƃł��ˁB
����ł��g���u���ɂȂ����Ƃ��͂ǂ����܂��傤(�j
�������S���ӎӍ߂������Ƃł��B
���ꂵ������܂���B
�����������N����{�点�Ă��܂������Ƃ�����܂���c
�֎��ւ����������������W�ŁA�����̏��Ԃ����ꂽ���Ƃɓ{����
�u���������I�v
�Ƌ��ۂ���܂����B
�������̔z��������Ȃ��������Ƃ������ł����̂ŁA�Ђ�����ӂ�܂����B
�ǂ��Ȃ����ł��傤�c
�������̕������ނȂ������̓��͓����Ē����܂���ł����B
�������\��ʂ�ɂ͂����Ȃ����̌���ł͂悭���邱�Ƃł��B��������ł��d������܂���A������͍אS�̒��ӂ��Ă��܂��B
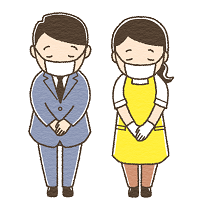
�������ȗ�������܂��B
���̎{�݂Ŏ��ۂɍ������P�[�X�ōl���Ă݂܂��ˁI
���10�l�̃f�C�T�[�r�X�B1���̃X�^�b�t��4�l�ł��B
60��̒j���l�����p���邱�ƂɂȂ�܂����B
��N���̔F�m���ł��B�w�������A�Ⴍ�Č��r�ŁA�Ⴂ���ɏ��ю����@���K���Ă��܂����B
�f�C�T�[�r�X�ɗ��Ă��{�݂ɓ��肽����Ȃ����A�����Ă���Ă������Ɂu�ƂɋA��v�Ƃ����܂��B�����ċA��Ȃ��Ɗ炪�������Ȃ�A�s�@���ɂȂ�܂��B
�������l����̓h���C�u�����Ă���Ɨ��������Ă��܂��B�{�ݓ��ł̊炪�E�\�̗l�ł��B
�����ǂ����܂��傤�H
�X�^�b�t���M���M���Ȃ����ɁA
�}���c�[�}���ł̉�삪�K�v�����ł��B�ł�����������4�l��10�l�̃P�A���A3�l��9�l�����邱�ƂɂȂ�܂��B
����D�悷�ׂ��ł��傤�H�ǂ�����ΐl����������ɗǂ��P�A���ł���̂ł��傤���H
���_���猾���܂��ƁA
�������́A���Ƃ����Ď{�ݓ��ɂƂǂ܂��Ă��炤�̂ł͂Ȃ��A�ق�1���}���c�[�}���Ńh���C�u�ɏo�����I�т܂����B
���̗��R��2����܂��B
�@�l���h���C�u���͂ƂĂ����₩�Ȋ�Ŋy�����߂����Ă��邱�ƁB
�A�l����Ɏ{�݂ɂƂǂ܂��Ă�����Ă���ƁA���݂��ɕs�s���������̂ł��B
|
�@�Ɋւ��ẮA�����͂���Ȃ��ł���ˁB��������
���̏Ί炪����������d�������Ă����̂ł�����B
���͇A�ł��B�l�����{�l�̈ӂɔ����Ď{�ݓ��ʼn߂����Ă��炨���Ƃ���ƁA�ǂ�Ȃ��Ƃ��N����̂ł��傤���H
�܂��́A�u�A��v�u�A��Ȃ��Łv�̂����ɂ���āA
���݂��̊W�������Ȃ�܂��B
���ɁA
4�l�̃X�^�b�t���c��̂Ŋm���ɐ��͑����̂ł����A�l����̋@���������Ȃ�A1�l�őΉ����Ă����X�^�b�t�ɁA
1�l�܂�1�l�ƃX�^�b�t��������(�j����Ă��܂��B
����1�l�̗��p�҂�3�l�Ō��Ă���Ȃ�Ă��Ƃ��N����̂ł��B�F���̎����ɋC�Â��ĂȂ��̂ł��B���̎��Ԃ͑��̗��p�҂ɋC��z��܂���A������ł�����B
����ɂ́A
���̗��p�҂̑O�ŁA�X�^�b�t�Ɓu�A��v�u�҂Ă��āv���J��Ԃ��ƁA�l����̕]����������܂��B���܂�ǂ���ۂ�������Ȃ��Ȃ��̂ł��B
�u
���N���ɒp���������Ȃ��v�Ƃ����̂�
���̌����ł�����A������������ʂ����Ȃ��z�����K�v�ɂȂ�܂��B
1��1�̃h���C�u�͈ꌩ���Ă݂�Ɣ�����I�ŗD�悷�ׂ����Ƃł͂Ȃ���������܂���B
�������A
���_��ς��Ă݂Ă݂�ƁA������I�ȉ��(�h���C�u�j�ɂ��g�[�^���Ō���ƌ����I�Ȗʂ������̂ł��B
�{���̌������l����ɂ͍L�����_���K�v�ł��B
�ڐ�̌����ɘf�킳�ꂸ�ɁA�g�[�^���ōl����Ə�肭�������Ƃ�����܂��̂ŎQ�l�ɂ���ĉ������ˁI
�@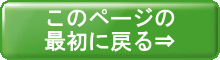
�G�ɐ��X�̃I�y���[�V�����Ɋw�� |
�ŏ��ɁA���f���ĐӔC������A�P�A�̌���̃��[�_�[��Ǘ��҂��ł���l�i�l�ށj���K�v���Ə����܂����B
���̗��R��������܂��B
�����������b�ł����A�Ⴆ�ΒN�����m���Ă���u�L�q�̉����v�ł́A���������Ƃ��ɂ́A
�������Ă���ŒZ�ŗ������ł���悤�ɁA���[�_�[�I����̐l�������S���̃X�^�b�t�Ɏd��������U��܂��B
�����āA�����S���̃X�^�b�t�̎肪�Ă��Ȃ��Ƃ��́A���炪�����ɓ���܂��B
�t���[�ȗ���Ō���̏����āA���̏u�Ԃ̃`�[���Ƃ��Ă̍őP�������Ă����̂ł��B
�������̃��[�_�[�����Ȃ���ǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤���H
�����炭�������������u�Ԃ���A
�u�������v
�u�������v
�u���₨�O�����v
�u�������͖Z����(�j�v
�N���d���𐿂������������߂�̂Ɏ��Ԃ�������߂��Ă��܂��̂ł��B
����ɖ��Ȃ̂́A
�u���ܐl�肪����ĂȂ��Ƃ���͂ǂ����H�v
���C�ɂ���l�����Ȃ�
���Ƃł��B
�����̒�Y�ꂽ��A�x���Ȃ�����Ƃ��q����ɖ��f�������Ă��܂����ƂɂȂ�̂ł��B
���̌���ɓ��Ă͂߂�ƁA10�l�̃f�C�T�[�r�X���p�҂�����Ƃ��āA4�l�̃X�^�b�t�����܂��B
����4�l�̂���1�l�A�t���[�ȗ���̃��[�_�[����������̂ł��B
����
���[�_�[���A���p�҂���̏�d���̐i������āA3�l�̃X�^�b�t�����A����Ȃ��Ƃ��ɂ͎��瓮���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
4�l��10�l�̗��p�҂�����Ƃ������Ƃ́A4�l��4�l���p�҂ɂ��Ă��܂��A�c���6�l�̗��p�҂̏�����l�����Ȃ��Ȃ�܂��B
��������ƁA�s�ӂ̎��̂�A�N���[���ɂȂ���܂��B
�u���[�_�[1�l�c����3�l��10�l�͗]�v�ɑ�ςɂȂ�܂��H�v
����Ȏ�����܂����B
���̓����͂����ł��B
�u
���[�_�[�́A10�l�̗��p�҂̑i����\�����āA���ꂪ�d�Ȃ�Ȃ��悤�ɃP�A�ɓ����鎞�Ԃ����炵�Ȃ���3�l�̃X�^�b�t�ŗv�]�ɉ������B�v
���́u
�P�A�ɓ����鎞�Ԃ����炷�v�Ƃ����̂��|�C���g�ł���A���[�_�[�̘r�̌������ł��B
�����āA�P�A�̎��Ԃ��d�Ȃ肻���ȂƂ��́A
�D�揇�ʂ��ԈႦ�Ȃ��悤�ɁA�����҂Ă�l�ɂ͏��Ɍ����đ҂��Ē���������Ă����K�v������܂��B
����
�D�揇�ʂ̌��f�ƌ��͂�����ł��ˁB
�P�A�̌���̃��[�_�[��Ǘ��҂��ł���l�i�l�ށj�́A���̂悤�Ƀt���[�̗���œ����Ă݂ĉ������B
�ԈႢ�Ȃ��l��s���͉������܂���I