�z�[���y�[�W�������̊F�l�A�͂��߂܂��āB
�R�����⍑�s�ŏ��K�̓f�C�T�[�r�X���^�c���Ă��铡�{�ł��B
����23�̎��ɉ��̐��E�ɑ��ݓ���܂����B���C�Ҍ��C(�w���p�[2���j�Ȃǂ̎��i������Ă��猻��ɓ������̂ł͂Ȃ��A
��Q�҂̉��s�{�����e�B�A�����������ɉ��Ƃ����d����m��A��w���ƌ�̏A�E�̂��Ă������������Ƃ���A�u���ł�����Ă݂悤���Ȃ��c�B�v�Ƃ������x�̋C�����ʼn����n�߂܂����B
����ȗ����̎d���̊y�����Ƀn�}���Ă��܂��A�����{�ʂ�6�̐E��(�K������E�O���[�v�z�[���E�V�l�ی��{�݁E�f�C�T�[�r�X�E�K����E�h���E���j��n������܂����B
�r���A�u�V��������v�Ƃ����V�N�ȍl�����ɐG���@��������܂������A�����������{�݂́A���N�����\�c�ꗍ���Ɉ����l�ȂƂ���Ŕ[���ł��Ȃ����Ƃ����X����܂����B
�u�������[���ł���d��������ɂ͎����œƗ����邵���Ȃ��c�v�ƍl���A
7�ڂ̐E��Ƃ��āu���̕ւ�v�𗧂��グ�܂����B�Ɨ���ɂ��l��s���ɂ�鎖�Ƌx�~���o������ȂǁA���]�Ȑ܂�����Ȃ���A��������22�N�Ԃɓn����̐��E�ɂ����b�ɂȂ��Ă��܂��B

����22�N�̊Ԃɉ����߂�����͑傫���ς��܂������A
���̌���͂RK�̎d���ƌ����A�h�����ꂪ���Ȃ��Ƃ͕ς���Ă��܂���B
�����āA�����d���Ƃ��ĂȂ��l�ɂƂ��Ă��A���������������邱�Ƃɕs��������l�������Ǝv���܂��B
�������A���̌�����o�������l�ɂƂ��ẮA��ς��̒��ɂ��A�y����������������d�����Ǝv���l�͏��Ȃ��Ȃ��͂��ł����A
�����邱�Ƃ͒p�����������Ƃł͂Ȃ��Ƃ����̂͌����܂ł�����܂���B
���̃R���e���c�ł́A��������ŏo��������N������̐��҂�������w���Ƃ����ƂɁA
�u�f�C�T�[�r�X���̕ւ�v���́u��삪�y�����Ȃ�l�����v�ɂ��ď����Ă��������Ǝv���܂��B
�����āA���R�ł������ꂩ�珑�����Ƃ����̂��ׂĂł͂���܂���̂ŁA�ǂ����C�y�ȋC�����œǂ�ł݂ĉ������ˁB
���ɑ��錩����l�����������ς���A���͖{���͊y�����d���ł��邱�Ƃ�m���Ă��炤�ƂƂ��ɁA
���X�̉�삪�y�����Ȃ�q���g��1�ł������Ă��炢�A
�܂������̉����邱�Ƃւ̕s���������ł��a�炰�邱�Ƃ��o�������ȂɊ��������Ƃ͂���܂���B
|
�����A�ꏏ�ɁA�y�����P�A���͂��߂܂��傤�I
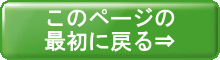
���̃R���e���c�ł́A���������Ȃ��u�y�������v�Ȃ̂��H�ɂ��čl���Ă݂����Ǝv���܂��ˁB
�����Ȃ�ł�������ł��B
���܉��̌���œ����Ă���F����́A�����̂���Ă������"������"�Ǝv���Ă��܂����H����Ƃ�"�Ԉ���Ă���"�Ǝv���Ă��܂����H
������Ɠ�����̂��������ł����ˁB�����悤�ȉ�������Ă��Ă�"������"�Ɠ�����l������A"�Ԉ���Ă���"�Ɠ�����l������ł��傤�B
����ł͂����ЂƂ���ł��B
���܉��̌���œ����Ă���F����́A�����̂���Ă������"�y����"�ł����H����Ƃ�"�y�����Ȃ�"�ł����H
����Ȃ班���͓����₷����������܂���ˁB
�Ȃ��Ȃ�A�y�������ǂ�����"��"����������Ȃ��̂ł�����B
�@�������������ĉ��H
���ی����n�܂���20�N���߂��܂����B�c��̐��オ75���}����2025�N���Ɍ����āu����Ȃ���l����v�Ƃ͂悭���������̂ŁA
�V�l�ی��{�݂�O���[�v�z�[���A���K�͑��@�\�{�݂ȂǁA�����J���Ȃ̍l�������x�͑�R����܂�����
�u�����łǂ�ȉ�������̂��H�v�Ƃ����̐S�̉��̒��g�ɂ��Ă͂قƂ�Njc�_����邱�Ƃ͂���܂���ł����B
�������Ȃ���A����܂łɉƑ��̉��Ɍg��������Ƃ̂���l�������d���Ƃ��Ă���l���A������͎������g�̂���Ă�����ɂ���
�u
���̂���Ă�����͖{���ɐ������̂��낤���H�v�Ƌ^���s�������������Ƃ�����͂��ł��B
���͈�Âƈ���ė��j�̐�
���ɂ͍����̂�������[���ł���"����"������܂���B
���ی����n�܂��������ɔ�ׂ�A���݂͉��Ɋւ��鏑�Ђ������o�ł���Ă��܂����A���̒��g�͐獷���ʂŁA�ǂ��M��������ǂ���������܂���B
��������̂͂��ł��B���Ƃ��Ăǂ�����������ڎw���Ƃ�������������܂��Ă��Ȃ��̂ł�����B
�����Ă��ꂩ����A���������āu
�ڎw���ׂ�����v�̒��g�ɂ��ċc�_�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ������ł��B
���̂悤�Ȋ��̒��ŁA�`���̎���̂悤�Ɂu���Ȃ��̂���Ă�����͐������ł����H�v�ɓ�����̂͏�������������ł��傤�B
"�l��"�Ɋւ��
��Âɂ́A"����"�Ƃ�"����Ȃ�"�̔��f�������܂��B
��w�I�ɍl����A����̂��������āA����Ȃ��̂��ԈႢ���Ƃ������܂��B
����ɑ��ĉ��͐獷���ʂ�"�l��"�Ɋւ���Ă��܂��B
�ł�����A�u���Ȃ��̂���Ă�����͐��������H�v�ƕ�����āA���M�������āu�������v�Ɠ�������l�͂��܂肢�Ȃ��Ǝv���܂��B
�Ȃ��Ȃ�A���������K���A�������i�A�����o���̐l�͂��Ȃ��̂ł�����B
����ł��A�ڎw���ׂ����̕������m�肽���ƍl����Ȃ�A"������"��"�ԈႢ��"�Ƃ͈قȂ锻�f������K�v������܂��B
�ʂ����Ă���Ȃ��̂͂���̂ł��傤���H
�@�����ꂩ��̉��́u�y�����v����ɍl����
�������̃f�C�T�[�r�X�u���̕ւ�v�́A
�w�������@�y�����P�A�A�͂��߂悤�B�x
�ƃL���b�`�R�s�[�����Ă��܂��B
���́A15�N�O�ɓƗ�����Ƃ��ɁA�u�������[���ł���d�����������v�Ǝv���Ɨ����܂����B
����́u�������y�����Ǝv����d�����������v�Ɠ��`��ł��B
�����Č��ł���ˁc�l����1/3�̎��Ԃ��߂�d�����y�����Ȃ��Ȃ�āc
�����āA����ȋC�����Ŏd����������E�ɉ����邨�N���ɂƂ��āA���̎��Ԃ��y�����Ȃ����Ƃ͗e�Ղɑz���ł��܂��B
���̎��Ԃ͖����f�C�T�[�r�X�ʂ��l�Ȃ�l����1/3�A�����{�݂Ȃ�l�����̂��̂ł��B
�����̌���œ����Ă���F����́A�����̂���Ă���d����"�y����"�ł����H
�F����̉����Ă��邨�N����"�y������"�ł����H
�킽�������̍l����u�ڎw���ׂ����̕����v��m��V�������f��́A
��삷�鑤�������鑤��"�y����"��"�y�����Ȃ�"��
�ł��B
�������u�y�����v�̉��l��́A�l���Ɋւ����Ɠ��l�ɐ獷�����ł�����A
�������̍l����u�y�����v�Ƃ��Ȃ��̍l����u�y�����v�͈���ē��R�ł��B�����ĉ����邨�N���ɂƂ��Ă��u�y�����v�̊���Ⴄ���Ƃ����R�ƌ����܂��B
�@�������y��������l����
�������̐��E�ɓ�����22�N���߂��܂����B�ق��闧���7�N�A�Ɨ�����15�N�ł��B"�y����"����"�y�����Ȃ�"�����o�����Ă��܂����B
�Ɨ������o�c�҂ƌ����Ă��l���X�̂悤�ȏ����Ȏ��Ə��ł�����A������������ł��N���Ɋւ���Ă��܂��B
���ꂩ�炨�`������̂́A�������̍l����
�u�����y��������l�����v�ł��B
�ǂ����C�y�ȋC�����ł������������ˁI
�B���Ƃ́u���������v���x���邱�� |
���u���������v�Ɓu���ɂ����Ȃ��v
�����ł͎����悤�ȈӖ������C���[�W�̂���2�̌��t�ɂ��čl���Ă݂����Ǝv���܂��B
"��������"��
"���ɂ����Ȃ�"
�F����͂���2�̌��t���牽���C���[�W���܂����H
�Q�l�܂łɕ��̕ւ�̃~�[�e�B���O�ŏo�������́c
"��������"�̃C���[�W
�@�E��]�E���C�Ȑl�E�ꏏ�ɁE�����E�P�������E�O����
|
"���ɂ����Ȃ�"�̃C���[�W
�@�E�ے�I�E��]�Ɍ����āE�����ɕK���ɂ����݂������E�킪�܂�
�@�E�����������ǐ������Ȃ����玀�ɂ����Ȃ�
|
"
��������"��
"
���ɂ����Ȃ�"�𗼕������Ă�l������c�Ȃ�Ĉӌ�������܂����B
"
���ɂ����Ȃ�"�Ƃ������t�̑�\�I�Ȃ��̂�"�a�@"�ł��ˁB
"
���ɂ����Ȃ�"�����f�����A���������A���Â�����̂ł��B
����"
���ɂ����Ȃ�"�ɂ�������̂́A�Ⴆ�u�����ɗǂ��v��
�e���r�ŏЉ�ꂽ�H�ו������̓��ɂ̓X�[�p�[�Ŕ�����Ƃ������悤�ȍs���߂������N�u���������ł��傤�B
���ł����Ȃ�"�R���i�E�C���X"�Ŏ��l�����Ȃ��l�ɑ���"��排���"��"
���ɂ����Ȃ�"
�Ƃ����v�����������邪�̂̍s����������܂���B
�@"���ɂ����Ȃ�"����a�@�֍s���B
�@"���ɂ����Ȃ�"���猒�N�u���ɂȂ�B
�@"���ɂ����Ȃ�"����R���i�Ŏ��l���Ȃ��l�ɑ��Ĕ�排���������B
|
�ł�"
��������"�͂ǂ����������t�Ŏg����̂ł��傤���H
�@�����Ǝ��R��"��������"
�@�F�m�ǂ��Q�ɂȂ��Ă������炵��"��������"
�@��肽�����Ƃ�D���Ȃ��Ƃ������"��������"
|
����2�ɂ͖��m�ȈႢ������̂ł��B����͂����������ł��傤���H
�����"��]"����o�����t��
"�|��"����o�����t���Ƃ����Ⴂ�ł��B
�������"��������"��"��]"����o�����t��
"���ɂ����Ȃ�"���|��"����ł����t�ł��B
2�̌��t�����̏�ʂɓ��Ă͂߂Ă݂܂��傤�B
�@�D���Ȃ��̂�����������̂�H�ׂ�"��������"
�@�F�m�ǂ��Q�ɂȂ��Ă������炵��"��������"
�@�a�C�����邯�ǖ������y����"��������"
|
�@���ɂ����Ȃ�(�]�т����Ȃ�����)���炢���x�b�h�ɂ���B
�@���ɂ����Ȃ�(�뚋�������Ȃ�)���痬���H����B
�@���ɂ����Ȃ�(������������Ȃ��j�����͎g��Ȃ��B
|
�ǂ��ł��傤���H
"
��������"�ɂ͎������ɂ��Ċ��O�����ȈӖ����������܂���ˁB
����"
���ɂ����Ȃ�"�ɂ͋��|�����Ȃ��̂������Č������ȈӖ����������܂��B
2���ׂĂ݂��
"
��]"����o��"
��������"
�̕���"
�|��"����o��"
���ɂ����Ȃ�
�����l�����y�������ȋC�����܂��H
�a�@�֍s�����Ƃ⌒�N�u���ɂȂ邱�Ƃ������̂ł͂���܂���B���Â̕K�v������Ƃ��͕a�@�֍s�����Ƃ���ł����A�H�ו��ɋC���������Ƃ��K�v�ł��B
�������A�a�@(
���ɂ����Ȃ��j��މ@�����
�����͐���(
���������j�̏�̂͂��ł��B
�܂�
"���ɂ����Ȃ�"��"�a�@"
"��������"��"�a�@�ȊO�̐����̏�"
|
�Ƃ����܂��B
"
�a�@�ȊO�̐����̏�"�Ƃ͂������"
���̏�"�̂��Ƃł��B"
���̏�"��"
���ɂ����Ȃ�"
�Ƃ����u���ɂȂ�A�����̏��a�@�ɂ��Ă��܂��̂ƈꏏ�ł��B
����͂���ƕa�@����މ@�ł����Ǝv�����̂ɁA�����ɂ܂��a�@��������(�j�Ƃ������b�̂悤�Ȕ߂����b�ł��B
�ł�����A"
�����̏�"�ōs������́A
"���ɂ����Ȃ�"���"
��������"���x���邱�Ƃ��ƂĂ���Ȃ̂ł��B
���͎��������l����悤�ɂȂ������������͂����̖{�ɂ���܂��B
���̖{�Ƃ́A
�u���E��A�������̎d�������悤�v�@(�_�ꏑ�[�j�ł��B
�������ƃ��n�r����������
�O�D�t������(���w�Ö@�m)��2008�N�ɏo�����{�ł��B
���̈�߂ɂ��������Ă���܂��B
|
�w�A�W�A�͐��������A���������ƌ����Ă���B���[���b�p�͎��ɂ����Ȃ��A���ɂ����Ȃ��ƌ����Ă���x
�`�����`
������u���ɂ����Ȃ��v���߂ɁA�V�l���o���_�i�������ăG�A���r�N�X�ɗ�݁A�݂̂��̔ԑg�����Ă͐H�i�̔�����߂ɑ���B����͕s���N�ł͂Ȃ����B
�`�����`
���Ƃ��ǂ�Ȃɕn�����Ă��u���ɂ����Ȃ��v���́u���������v�̂ق������N���B������̂ɕK���Ȑl�̓G�A���r�N�X���[���̔�����߂����Ȃ����낤�B
�`�����`
�������́u������v�P�A���������B�u���ɂ����Ȃ��v�P�A������̂͌����B
���\�h�A�g���A�]�g���c�A�݂�ȁu���ɂ����Ȃ��v�Ɍ}���������̂ł͂Ȃ����B
�������͐����Ă��Ă��d�����Ȃ��A�Ɗ����Ă����l���A����1�x���̐g�̂Ő����Ă������A�Ǝv���悤�ȃP�A���������̂��B
|
���Ȃ݂ɁA�u���̕ւ�v�̃~�[�e�B���O�̍ۂɁA�u�ǂ���̐�������I�Ԃ��H�v������A6�l�S����"
��������"��I�т܂����B
�F��������ǂ����I�т܂����H
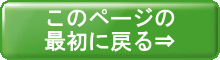
�u�y�������Ƃ͉����H�v���l�����ł́A��ÂƉ��̈Ⴂ�𗝉����Ă������Ƃ���ł��B
���̂��߂Ɉ�Â�����̂��H�Ɩ����A�u�����A
���Â����v�ׁA�Ƃ��������ɂȂ�͖̂��炩�ł��B
�ł͉��͂ǂ��ł��傤�B���̂��߂ɂ���̂ł��傤���H
��Â̖ړI�@�@�@�@�@�@���̖ړI
�����@�@�@�́@�@�@�@�y�@�@�@�@�z
���Â���@�ˁ@�@�@�@�y�@�@�@�@�z
�l���ň�Â������Ƃ��Ȃ��l�͂��Ȃ��ł��傤���A���������Ƃ̂Ȃ��l�͂قƂ�ǂ��Ǝv���܂��B
������ł���C���[�W�͂́A�u�����b������v�Ƃ��u�I���c��ς���v�Ƃ��u�H����H�ׂ�����v�ʂł��傤�B
����͌����ĊԈႢ�ł͂���܂��A�u�ړI�����̂��߂ɁH�v�ƍl����Ƃ�����ƈႤ��������܂���B
���
�u�����A
�������v
���߂ɂ���Ƃ���Ȃ�A����
�y��炷�z��
�y��������z
���߂ɂ���A�Ƃ��������t�̕����������肫�܂��ˁB
�����ł��B�u�I���c��ς�����v�u�H����H�ׂ�����v�Ƃ�������̓I�Ȃ��Ƃ̐�ɂ�
�y��炷�z��
�y��������z
������܂��B
��Á��a�@�����Â̏ꁁ�y�����z�@�y���Â���z
��쁁�ݑ�����̏ꁁ�y��炷�z
�y��������z
|
�������F���Г��ɓ���Ă����Ă��������ˁI
�������卷�Ƃ����܂��B��ÂƉ��̈Ⴂ��m���Ă��������ŁA�c��̐l�����y�������y�����Ȃ����ɑ傫�ȍ����ł�̂ł��B